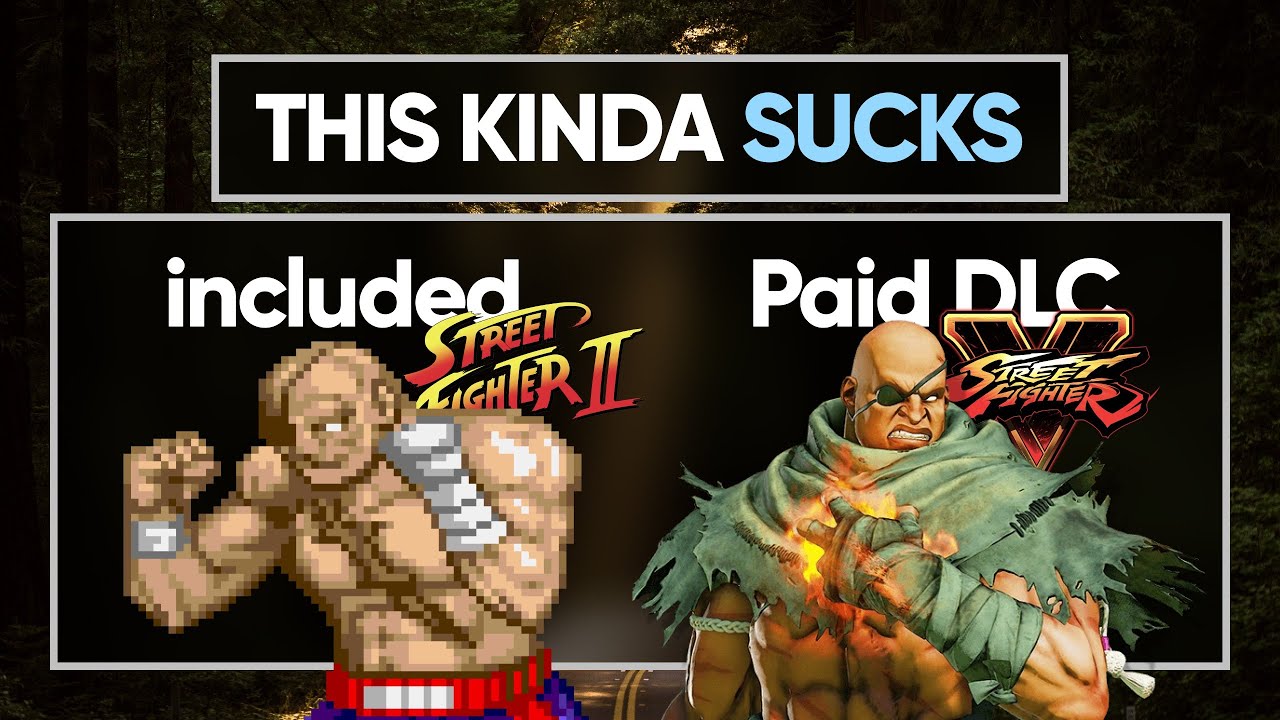空隔の街・新宿
9.12.20<br /><br />新宿は本にならない<br /><br />私たちは、新宿駅構内の片隅に「ベルク」という飲食の店を構えています。「私たち」というのは、ここに紹介する写真を撮った迫川尚子が、共同経営者の一人だからです。ついでに、彼女は私の同居人でもあります。15年分、新宿駅周辺を中心に撮りためたので、新宿をテーマに一冊の本を出したい、と迫川に相談されたとき、私は賛成しませんでした。かと言って、反対する立場でもなかった。お金はかかるけど、私のお金ではないですし。<br /><br />せっかく時間をかけ、撮って焼いたものを、そのまま眠らせておく手はない。店や路上では既に展示していましたし、何らかの形で発表することに私も異論はありませんでした。ただ、写真集という形式をとるのが、ぴんとこなかった。単なるメモリアルではなく、世に問う作品にしたい、と本人の意気込みは強く、協力者にも恵まれ、私も拙いながら文章を寄せ、名づけ親にもなりました。結果的に写真集『日計り』(1)の出来栄えは、想像以上に素晴らしいものだった。が、どうも「新宿」的ではない気がしたのです。本にすること自体が。<br /><br />撮影には、何度か同行しました。何を考え何に悩んでいたのか覚えていませんが、じっとしていられなくて、新宿の街をがむしゃらに歩いた、10代20代の頃の自分に戻ったような気分でした。迫川がシャッターを押せば、私も立ち止まり、煙草をふかす羽目になります。だから、一人のときとは歩き方が違います。ただ、何を撮っているのかと相手のことが気になる訳ではなく、たまに思いもしない方にカメラが向いていても、それを横目で「ふうん」と見るくらいでした。街中、無数に氾濫する情報の、その一つ一つに、私は私で反応しているのです。が、そのあまりものとりとめのなさに呆然となりました。<br /><br />職場「ベルク」も、新宿の雑踏の中にあるせいか、めまぐるしく仕事に追われながら、やはり呆然となることがあります(雑踏のせいにしてはいけない?)。新宿は、四六時中、色々な人が大勢来て、帰っていきます。今、来たところか、帰るところか、ただの通りすがりかすらわからない。それぞれ、様々な目的や成果があるでしょう。何のあてもない人もいるでしょう。それらの人たちと、接することもなく接しているうちに(低価格高回転の店でなかば流れ作業的な接客です)、だんだん無方向で無時間な感覚にとらわれます。<br /><br />「新宿」をテーマにしたと言われる映画をいくつか見ましたが、どれも違う、と思いました。新宿はほんの背景に過ぎない、と言うか、そもそも物語におさまりようがない。本も、映画よりは頁をめくり直したり、マイペースで読む自由はありますが、始まりと終わりがある以上、どう並べても、何らかの意味と方向性が生れてしまいます。それが、私には「新宿」的ではないと思えたのでしょう。<br /><br />むしろ、明確な方向性がないと、出版社には持ち込みにくい。迫川が用意した写真は、本にするには十分過ぎるほどそろっていました。「犯罪都市」とか「風俗の街」という観点から興味本位に語られる新宿はあくまでもよそゆきの新宿であって、もっと日常的な普段着の新宿でいきたい……確かに、私たちにとってそこは「いつもの場所」です。編集を引き受けて下さった写真家の金瀬胖さんも、その路線でタイトルを考えられていたようです。それ以外にまとめようもなかった。ただ、どうやってもしっくりこない。写真が裏切るのです。<br /><br />その頃、「くうかく」という言葉があるのを、ある雑誌(2)で知りました。新宿でビル清掃の仕事をしていた詩人、山本陽子の詩は、既成の辞書では殆んど解読不能です。ただ、それらを造語と呼ぶのもためらわれるのは、作者の見えすいた手口が感じられないからでしょう。むしろ、言語そのものが連鎖的に突然変異を起こしている。「くうかく(空隔)」も、その一つです。対象があるようでない、しかし、どこかにそっと触れられている(実際、手に触れてみたくなる(3))迫川の写真のありようと、その言葉の輪郭は似ている、と思いました。<br /><br />「空隔」をタイトルの候補にしたとき、金瀬さんは、それまで試行錯誤を繰り返していたダミー本を全部ばらして、空中に放り投げたそうです。それは放棄を意味した訳ではありませんでした。ただ、無方向で無時間の混沌の中へ、一度、自ら身を投げられたのかも知れません。<br /><br />(1)…迫川の生まれ故郷、種子島に生息する毒蛇の名前。<br /> 噛まれたら、その日ばかりの命と言われる。<br /> ただし、実際には無毒。<br />(2)…『重力02』中島一夫氏のスガ秀実論。<br />(3)…森山大道氏は、迫川にコメントを求められると、<br /> 何も言わず、写真を撫でたそうだ。<br /><br />(井野朋也/『自然と人間』2005年3月号グラビアより)<br /><br />山本陽子さんが清掃員として働いていた新宿西口の安田生命ビルは、段ボールハウス村と目と鼻の先。運命を感じました。<br /><br />この映像で使われた、2枚の写真、<br />1枚目は「北新宿百人町交差点」(1993年)<br />2枚目は「甲州街道付近」(1994年)<br />です。2枚目は女子美の広報誌の表紙にもなりました。土門拳賞受賞作家でベルクのギャラリー顧問でもあった鈴木清さんは、一度発表された人の作品に対し、コメントはしないというのがポリシーでしたが、私が「あえて」お願いすると、この「甲州街道付近」の画面の右上のほう、黒い部分を指して、「あなたの撮りたいのは、ここでしょう」とおっしゃったんです。「こ、ここかー」まじまじと自分の写真見ちゃいました。<br /><br />(迫川尚子)<br /><br />ここに最近刊行されたばかりの一冊の写真集がある。『日計り』(迫川尚子著、新宿書房)と題されたその写真集は、新宿駅ビル地下のビアカフェに勤務する一人の女性が、本人あとがきに曰く、毎日地下に潜伏する「モグラのような生活」の合間合間をぬって地上に顔を出し、頭上に広がる新宿の街にカメラを向け続けてきた記録の集積である。<br />そこには、全てのショットが九0年代以降に撮影されたとはとても思えない、戦後のバラック街のような新宿が広がる。朽ち果て崩れ落ちたコンクリートの破れ目からのぞく土、泥、草。廃品同様の一昔前のテレビ。ガラスの割れた横丁の電飾看板。ホームレスのダンボールハウス……。視線が向かう先は、戦後の高度経済成長が開発し均質に均し損なった"残余"であり、あるいは地上=表層に塗り固められた"成長"の物語が剥がれ落ちたその"カケラ"である。<br />これらの新宿が一向に暗さを帯びないのは、モグラが"カケラ"を見つけては嬉しそうに戯れているからだ。その姿は、やはり残存する「路地」を求めて新宿にやってきた中上健次や、空襲下の瓦礫のそこかしこに「白痴」の顔を見出しては享楽に耽った坂口安吾を彷彿させる。そして、林芙美子が闊歩したたずんだ新宿も、またそのようなものではなかったか。<br />今や『放浪記』を論じる誰もが参照する『モダン都市東京』の海野弘は、「終戦後のバラック時代の遺物だと思っていた」横丁が、「『放浪記』によれば、一九二0年代にすでにあったようである」と述べている。最も計画的に都市化されたようでいて、その実つぎはぎ的場当たり的に発展していった新宿には、戦前戦後を通底する"カケラ"が、見ようと思えば至る所に見出せる。<br /><br />(批評家・中島一夫の林芙美子論『掲示板の詩(うた)』より)<br /><br />※『日計り』という写真集の方向性は、私たちが『重力02』という雑誌に掲載された中島一夫さんのスガ秀実論『隣接に向かう批評』を読んで、触発され、決定付けられました。<br />※『隣接に向かう批評』は、ベルク本とほぼ同時期に出版された『収容所文学論』(中島一夫著、論創社)でお読みになれます。<br /><br />(井野朋也)<br /><br />詩/山本陽子<br />写真/迫川尚子<br />音楽/井野朋也





![Minecraft Frozenopolis | EXOFLAMES & FUELLESS ORE PROCESSING! #6 [Modded Questing Survival]](https://i.ytimg.com/vi/CB2r5RFX7gk/maxresdefault.jpg)